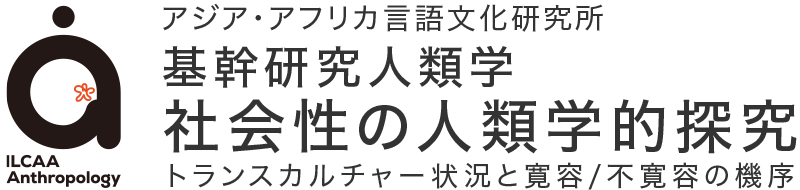「体制転換の人類学」2016年5月開催報告
<開催報告>
日時:2016年5月20日(金)14:00~18:30、5月21日(土)14:00~19:00
場所:東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 マルチメディア会議室(304室)
参加者:5月20日 24名(内外国人 0名)、5月21日 20名(内外国人 0名)
【内容】
〈5月20日〉
田沼幸子氏による『革命キューバの民族誌』の解題と、同じ登場人物の海外移住のその後を追った田沼氏による映画Cuba Sentimentalの上映を行い、それらをめぐる討議を行った。
『革命キューバの民族誌』は、現在のキューバを国内外の当事者の視点から描く人類学的研究である。キューバ革命以来、「体制転換」は何度も語られてきたが、それはすぐに覆され、忘れ去られ、ふたたび別の転換が注目を浴びると指摘する。本著は内側に住む人々がその「革命キューバの日常」をどのようにとらえているのかを、人々の日常からとらえようとした意欲的な著作である。
革命勝利直後の熱狂と、それが日常となるなかで生まれてきた問題に対して、革命家がどのように「人間」や「労働」を捉え直そうとしてきたのかを概観し、人々の親密な場における語りをとりあげる。そこから、革命の理想とは大きく矛盾した状況を露呈し、矛盾を公に語れない状況で、人々はダブルバインドにからめとられている現状を描く。田沼氏はダブルバインド下にある人びとが、非常期間を笑う様子を分析し、かつては自分も信じた理想が失われたことへの哀惜の念をともなうポスト・ユートピアのアイロニーとして示す。
3人のコメンテータは、それぞれの専門分野の立場からコメントした。カリブ海フランス文学を専門とする中村隆之氏は、フランス海外県であるマルチニックのエメ・セゼールとチェ・ゲバラが比肩しうることを指摘し、文学と民族誌の交点において、革命の物語を延命させるものとしてクエントに着目した。人類学者の佐久間寛氏も同じく、ポスト・ユートピア的アイロニーとしてクエントを取り上げ、田沼氏のクエント的民族誌を「新しい手触りの民族誌」として評価した。同じくキューバをフィールドとする大杉高司氏はその著作と映画を高く評価しつつ、人類学者が作成する民族誌映画ならではの意義について問題提起を行った。フロアーからも社会主義国のダブルバインド状況や移民におけるイデオロギーの内面化などをめぐって活発な議論が行われた。
(文責:西井)
〈5月21日〉
まず佐久間寛が「ハザードとしての体制転換」というタイトルで趣旨説明をおこなった。20世紀末から今世紀にかけて各地で生じた体制転換を、予測も制御も困難な不確実性の時代=ハザードの時代の到来と位置づけたうえで、人類学研究においては、そうした世界史的出来事の渦中を市井で生きた人びとの価値観や理想、文化表象や伝統的とされる諸実践の様態こそが重要であるとの主張がなされた。
次に神原ゆうこ氏による報告「体制転換後の村落における社会変容と人々の意思と実践:『デモクラシーという作法』自著解題を兼ねて」が行われた。報告者から事前に提出された要旨は以下の通りである(神原氏執筆)。
1989年に市民による社会運動の成果として社会主義からの体制転換を経験したスロヴァキア(当時はチェコスロヴァキア)において、民主主義という制度はその後の社会のありかたを方向付ける目標であった。その一方で、体制転換の恩恵を受けにくかった地域には、漠然とした不満が蓄積されている。本報告で注目するのは、体制転換後の世界への適応が困難であるとみなされがちであったにもかかわらず、EU加盟国の一員としての政治的な自律性を期待される村落の人々の政治的な価値観の変容である。本シンポジウムのテーマである「体制転換の人類学」に即して説明するならば、東欧諸国の体制転換の目的そのものである民主主義という理念と、それを支える市民社会というシステムのコミュニティレベルでの受容ないし適応について、本報告は文化人類学的な考察を試みるものである。
体制転換後のスロヴァキアの民主主義を理念的に支えるのは、「国家に対抗する/国家に頼らず必要なことを自ら行う」アソシエーションの自由な活動によって成立する市民社会であるが、現実にはそのようなアソシエーションはごく一部である。地域の自治を民主主義の基礎をして重視するEUの政策と、ネオリベラリズムの影響を受けて進められた地方分権化は、社会主義時代からマイペースに活動を続けていた村落のアソシエーションに新しい時代の模範的「作法」を導入した。村に利益をもたらす活動ができるアソシエーションは、その自律性ごと村落政治に取り込まれ、そうではないアソシエーションは存在の意味を失いかねない状況にある。ここで「市民」としての論理が、対面的な人間関係を崩さないために有効であるとはいい難い。その意味で、スロヴァキアの村落は、市民社会に包含されているが、そのシステムに支えられているとは限らない。多様な経験を持つ個人の政治的な価値観を集合的に把握するには、これらの具体的実践に注目する必要がある。
以上の発表に対しコメンテータの清水昭俊氏は、敗戦後日本の構造変革をひとつの参照軸にすえつつ、マクロな政治変動にミクロな人びとがどう参与したかを見る場合、国家がもつ意味はやはり大きく、ミクロな人びとの参与実践を把握するためにこそ、国家の巨大さをしっかり測っておく必要があるという指摘がなされた。
次に津田浩司氏の報告「体制転換とインドネシア華人:『「華人性」の民族誌』への著者解題」」が行われた。事前に提出された要旨は以下の通りである(津田氏執筆)。
1998年にスハルト体制が崩壊したインドネシアでは、その後「改革の時代」の名のもと、中国や華人にまつわるとされる文化要素を公的な場で表出することが解禁されたのみならず、中国正月(旧正月)が国民の祝日となったり、孔教(儒教)が再公認化されたり、あるいは華人系として初の「国家英雄」が認定されるなど、従来抑圧されてきた華人を取り巻く社会・政治的環境は大きく変わったのは事実である。そしてこれらの達成を以て、体制転換とその後の民主化により、インドネシア華人は抑圧から解放され自らの文化を自由に表象できるようになりつつある、と肯定的な評価を下したり展望することも不可能ではない。
しかし、人々の生活レベルを基盤に「華人であること」を考えた場合、上述の変化はいわばシンボリックな表象レベルのそれに過ぎないと見ることができる。5年前に上梓した拙著『「華人性」の民族誌―体制転換期インドネシアの地方都市のフィールドから』(世界思想社, 2011年)では、ある地方小都市において対面関係をベースにした相互認知の和として経験・イメージされる「華人コミュニティ」というものを仮の認識的足場として設定し、そこから超え出るようなあり方として観察される「華人であること」を批判的に捉える戦略を採った。本発表では、同書中で理論的な軸として設定した「顔の見える/見えない関係性」の対比を今一度強調しつつ、体制転換で伴い変わったもの/変わらなかったものの捉え方について、議論を喚起する。
以上の報告に対しコメンテータの内堀基光氏は、まず報告のもとになっている津田氏の著書を「おそろしく(面白く)読みやすい」と高く評価したうえで、(1)世界の華人研究との比較の視点があっても良かったのではないか、(2)華人内のカテゴリー(客家など)について記述する必要はなかったか、(3)ジャワ人に関する記述が不足していないか、(4)調査と同時代的な現象に関する記述と考察がより盛り込まれても良かったのではないか、(5)(4)の作業がなされたとき、いわゆる「真正な社会」の真正性が何に担保されているのかという根本的な問題が浮かび上がってくるのではないかといった問題提起を行った。
最後に松本尚之氏の報告「ナイジェリアにおける体制転換と王位/首長位:『アフリカの王を生み出す人々』への自著解題とその後」が行われた。まず「(1)アフリカにおける1990年代以降の体制転換」では、一党制から複数政党制へ、軍政から文民政権へという形で進んだ1990年代アフリカの体制転換が概観され、報告の主題が、こうした転換の最中に生じた「首長位の復活」と呼ばれる現象にあることが示された。「(2)調査地の概括」では、ナイジェリアにおける民族対立の歴史と構図が示された上で、報告者の調査地であるイボ社会の概要が紹介された。「(3)ナイジェリアの体制転換と「首長位の創造/復活」」では、植民地化以前のイボ社会には首長に相当する地位がなかった可能性が高いにもかかわらず、植民地化から独立を経て現在にいたる一連の史的プロセス――民政から軍政(1966年、1984年)および軍政から民政(1979年、1999年)への体制転換を含む――一において、当の住民が一貫して「首長位の創造」の過程に「主体的」に関与してきた点が論じられた。「(4)第四次共和制下における伝統的権威者の位置づけ」では、直近の政体である第四次共和制下のイボ社会において生じた首長(エゼ)を焦点とする3つの動態、すなわち①王政後めぐる自文化理解の変化、②「ローテーション制」と「ゾーン制」をつうじた草の根の民主化、③エゼの乱立と民主主義政権の関わりにが明らかにされた。最後に「(5)まとめと考察:ナイジェリアの体制転換と王位/首長位」では、これまでの議論をふまえた上で、たびかさなる体制転換を経てなお持続する首長位の強靱さ=「伝統的権威者たちの弾性」の重要性が指摘された。
以上の議論をふまえコメンテータの三浦敦氏からは、伝統首長の復活という現象が旧英領諸国に多く見られる現象であり、いくつかの例外をのぞき旧仏領アフリカ諸国では見られないこと(かといってそれは首長に相当する地位が皆無ということではなく、そうした地位はすでに近代行政システムのなかに統合されるかインフォーマルなかたちで存続しているケースが多いこと)が指摘された上で、こうした相違は英国流のcommon law とフランス流のcivil lawによる資源配置の違いに由来しているのではないかという示唆に富むコメントがなされた。
シンポジウムの取りまとめとして、最後に名和克郎氏から各報告への総合的コメントがなされた。デモクラシーや華人をめぐる「翻訳」の問題、地域によって体制をめぐる人びとの距離がまったく異なるという問題、体制転換を現在ではなく事後から見ることの可能性と限界、体制転換をハザードと捉えることへの疑問(誰にとってどの程度のハザードなのか)などが論点として提出された。これらの論点をめぐり報告者、コメンテータ、他の参加者による活発な議論が行われ、予定を30分超過しての閉会となった。
(文責:佐久間)