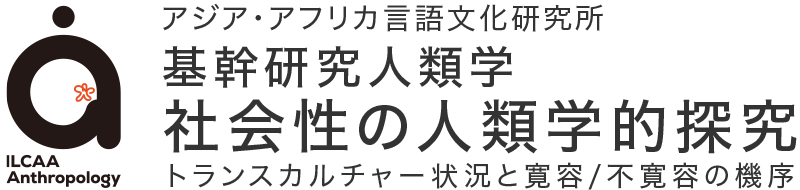コメント1:國弘暁子(早稲田大学)
(深澤) それでは、ここからコメンテーターの先生方のコメントと、その後それを受けて発表者、コメンテーター、最後に会場の皆さまを含めての全体討論という、最終のセッションに移りたいと思います。
最初のコメンテーターは、國弘先生です。國弘先生は、実は奄美沖縄研究とはほとんど関わりがありませんが、私の方から飛び込み営業でコメンテーターを無理にお願いした次第です。國弘先生は、インドのトランスジェンダーのヒジュラの研究を長くやられているのですが、最近はそこから世界的に視野を広げられまして、クイア(Queer)というふうなある種の違和感、おかしさというものを梃子に人間というものを見ていこうという非常に挑戦的な戦略を展開されている研究者です。その点で、沖縄とか奄美というものを知らないという点から大いに「暴れて」いただこうということでコメントをお願いしています。では、國弘先生、お願いします。
ご紹介ありがとうございます。國弘です。今まさに私の家族が危機的な状態にありまして、病気を互いにうつし、うつされながら、今第二ラウンドに入っております。私自身もひどい風邪をひいておりますが、そんな中、どうしてもこの研究会に参加したいという思いがありました。その理由は、もし、私がインドを調査地として選択しなかった場合、沖縄で行いたいという私自身の長年の思いと関係があります。今ではもう過去形になってしまい、今から沖縄調査を始める余力も無くなってしまいましたが、本日お集まりの先生方は沖縄で長年研究を続けられており、そのご研究の発表を直に伺えるというまたとない機会は逃すわけにはいかないという思いから、本日は体調不良ではありますが、何としてでも参加したいという思いでやって参りました。ご参席の皆様に風邪をうつすといけませんので、本日は恐縮ですが、マスクをしながら、コメントさせていただきたいと思います。
本日のシンポジウムでは、「家族」と「危機」というキーワードが掲げられておりますが、北インド社会で長年調査を行っておりますと、家族というのは「危機」そのものなのではないかなと考えるようになってきています。その場合の「危機」が意味しているものとは、例えば、子供が生まれるという出来事があります。生命の誕生とは、今まで目の前に存在していなかった生命体が突然やってくるという出来事ですから、全くの他人であって、自立できない生命体を受け入れる家族と称されるメンバーにとっては、危機をあえて迎え入れる覚悟を持って臨む必要があろうかと考えます。また、家族のメンバーの誰かが結婚となれば、外から他人が入ってくる、それも一つの大きな変化で、一般には「幸せ」と表現されますが、ある種の危機を乗り越える儀式を必要とするものと考えます。そして、家族のうち誰かが死ぬという出来事も、もちろん危機的な状況だと考えます。誕生や死、他人との婚姻は、ある程度の予測がつきますので、突如として襲いかかってくる危機に比べれば、衝撃の程度は低いものですが、やはり危機であることには変わりなく、限定的な家族だけで耐えるのではなく、よそ者の力を取り入れながら対処するという仕組みが、土着の慣習として出来上がっている、ということをこれまで考えてまいりました。
常態として在る「危機」の問題対処にあっては、土着の慣習によって、なすべきことが決められていますから、人はそれを粛々と成せばよいと思います。しかし、当然ながら、私たちが耐えなければならない危機とはそれだけではなく、全く予測もしていなかったかたち、あるいは予想を超える規模で襲いかかってくることがあります。本日の四名の先生方がお話しされた「危機」というのは、粛々と対処できるような問題ではない方の、後者の「危機」に関する事例であったと思います。例えば、戦争や災害、そして介護という問題は、よそ者が突如として自分たちの内側に入ってくる問題としてみることができます。ユタが家族の問題に関与してくるというのも、やはり外の力が突如入ってきて、内部に何か問題が起きる、という事例であろうかと思います。それぞれの危機を、どのようにして対処しているのかということを、それぞれの先生方が細かく、具体的な出来事の逸話を挟みながらお話ししてくださいました。私自身知らない事例がたくさんありましたので、とても興味深く話を聞かせていただきました。
このシンポジウムの企画について話を伺った時から、今に至って、気になっていることが一点ございます。それは、「沖縄の」という形容が付くことに関してです。沖縄という土地には観光客として関与したことしか私自身ありませんが、研究対象として、「沖縄」と言い切ることが、果たしてどこまで妥当なものなのか、この点に関して、本日ご発表いただいた先生方のご意見を聞いてみたいという思いがあります。
どうしてそんなこと考えるのかといいますと、先日終えが書評の仕事と関係しています。東大の瀬地山先生が編纂された『東アジアのジェンダーとセクシュアリティー』という論集の書評を書く仕事でした。瀬地山先生ご自身は、20年近く東アジアで調査を継続されてきた中で、大きなマップが見えてきたというお話を序論の中でされています。そのマップでは、コリアン、チャイニーズという線引きが可能となり、そこには入らない、もう一つの区分、ジャパニーズが存在するというものです。とりわけ興味深い点は、例えば、韓国と日本は、資本主義という点で近いように表面上は見えるけれども、それらの土壌に根付いているジェンダー規範、家族の規範という問題に目を向けてみると、むしろ遠いものとして理解することができ、共産圏の北朝鮮との方が、韓国は価値観の多くを共有しているところがある。そして、同じような主張が、台湾と中国においても言える。そのため、日本は東アジア圏内ではどことも接続を持たず、ジャパニーズという独立したカテゴリーが必要とされるという、考えを表現したマップが提示され、その議論を補強するかのような論文が収められて、大変興味深い論集でした。
そして、本日のシンポジウムにおける「沖縄の」という形容についてですが、もし、瀬地山先生が提示されたような東アジア圏のマップがこの場で出された場合、沖縄で調査をされている先生方はどのような配置を考えられるのか、この点に関心がございます。もっと具体的に申しますと、「沖縄の」という表現を使用することの妥当性はあるのかどうか、沖縄でしかない、というものが、実は、そこらにも転がっているということはないのだろうか。先ほど加賀谷先生からは、「沖縄の、というふうにも必ずしも言い切れないのではないか」というご意見がありましたが、沖縄だけにしかないものというふうに言えるようなジェンダー規範、あるいは家族規範があるのか、そうではないのか、ぜひ、そのあたりも聞かせていただきたいなと思います。
そして、沖縄で研究をしてみたかったという憧れを抱いていた者としては、もう一つお聞きしたい質問がございます。全く異なる言語圏まで飛行機に乗って行き、そこで調査を行っておりますと、日常の生活と調査地での活動との間にブランクが常につくられる状況にあります。最近はSNSですぐに連絡が取れますし、また、一方的にいつ何時でもメッセージが送られてくるので、日常生活と調査との境目がなくなりつつはあるのは事実ですが、しかし、沖縄で研究される場合には、そのブランクが非常に少ない、あるいは別の形をなしているのではないかと思います。日常ではない調査の機会と日常生活との線引きが曖昧な状態にある場合、調査者と調査される方々との関係性というものはどのようにつくられるのか、その調査手法について、ぜひお聞かせいただきたいと思っております。研究者である先生方が発言されることは、沖縄に住んでいる人々の耳には容易に届くでしょうし、その内容が、沖縄らしさというふうに一人歩きするようなことももしやあるのではないかなと、そんなことも想像したりしております。
それから、最近では、私自身は北インドだけではなく、フランスの家族の在り方についても興味をもって調査を始めておりますが、そこで、本当に些細な個人的なことですが、山内先生のご発表の中で、打越正行先生の『ヤンキーと地元』の事例を紹介しながらの議論にとても興味を持ちました。資料④を見ていて面白いと思いましたのは、沖縄における「島の原理」から外れた人たちの性の在り方だというご紹介がありましたけれども、「キャバレー」という言葉を除くとフランスでよくある事例であると感じられる点です。つまり、沖縄で逸脱として語られる状態が、フランスでは当たり前に一つのファミリーの形をなしているということを認識させられ、何故このようなことになっているのだろうかと、興味をもってお話を伺っておりました。そして、もし、フランスでこのような生き方と、そうではない生き方を良しとする考え方があるとするならば、それは何なのかということも同時に考えていました。おそらくですが、後者に相当するものとは、現代ではマイノリティにありつつあるカトリックのコミュニティーではないかと考えます。カトリックの教会を支える人たちが形成するコミュニティーで語られるファミリー像というものは、理想的なものとして容易にイメージをつくることのできる家族像であると考えます。昨今では、そうではない家族のかたちが実態として増えている状況にあるので、この差異のあり様について考える上で、山内先生のご指摘が非常に興味深いと思いながらお話を伺っていました。
以上になります。ありがとうございました。
(深澤) ありがとうございました。今、國弘先生から投げかけられたコメントについては、次の四篠さんのコメントが終わった段階で、討議したいと思います。このシンポジウムを開催した人間としましては、沖縄ということに取り立てて焦点を当てて議論をしたいというよりは、家族ということに焦点をあててシンポジウムを組みたかったと言うのが本意です。しかしながら、世界から家族に関する事例を集めてくるととほうもない多様性があるため、取りあえずは沖縄、奄美方言の中で議論すると少しはまとまるものがあるのではないかと考えた次第です。あるいは先ほど述べたとおり、奄美までは琉球王国の支配下にあった上、例えば神役制度であるとか、そういうものも共通性を持っているという点で、非常に危険な言い方ですけれども、「基層文化」的なつながりがあるのではないかという前提を設けています。